Live Aid index へ戻る
0720 Thurs.
抵抗線の使い方
30分ギャッププレイでは、銘柄を探すときや、脱出のポイントを探すときは、トレンドが形成する抵抗線を利用することで、「しらみつぶし」に銘柄を探す際の効率を高くすることができるということを、昨日書きました。早速ご質問をいただきましたので、ここで解説をさせていただきます。
なお金曜日には現在開催中の7月の米国株ライブトレードセミナーの一部を、セミナー会場から直伝を使って、インターネットで実況中継の予定ですが、この件についても、解説を予定しています。
こんにちは。2006年6月ジャンプアップセミナー受講の**と申します。いつも有難うございます。基本的なことで恐縮ですが、30分足の抵抗線につきまして質問があります。
7月19日“Cool”で30分ギャッププレイについて説明されている部分で、信越化学の30分足の抵抗線が6,560円とされておりますが、これまで私が抵抗線だと考えていたのは、前日7月14日の高値6,580円でした。
日足と同様に30分足でも、直近の本体高値が抵抗・支持線になるものと考えていたのですがどうも間違っているようですので、基本的な考え方につきましてご教示頂けますと幸いです。宜しくお願い申し上げます。(Wordファイルでチャートを添付いたします。)
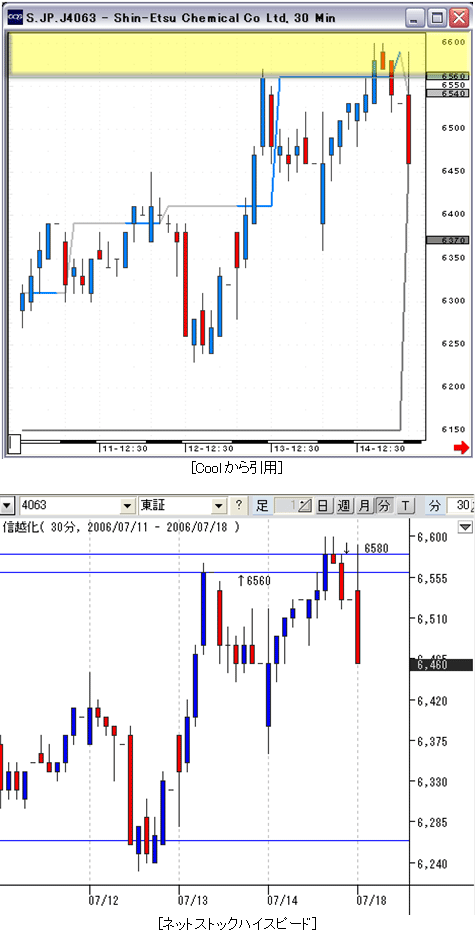
30分足の抵抗線6,560円と、抵抗線だと考えられていた、前日7月14日の高値6,580円はどちらも30分の抵抗線に変わりはありません。
ですから、ここの認識が間違っているわけではありません。
7月18日は6540円がオープンの株価ですね。
つまりこの位置から最も近い抵抗線の位置6560円が、まず最初に邪魔になってしまっている可能性があるということです。
6560円から株価が上昇して、6580円になって下がれば、抵抗線が6580円に新たに形成されたと考えるのは間違っていません。
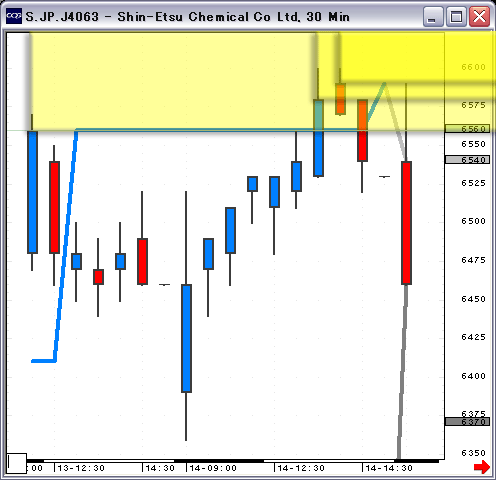
問題は6540円から始まった株価が6560円を突破できずに陰線で終わってしまったということです。
ということは、オープニングに最も近い6560円の抵抗線の影響が皆無ではなかったと推測できます。
12日に形成された6560円の抵抗線は、そのあとローソク足12本にわたって有効だったわけですから、かなり強力な抵抗線になっていたということです。
6580円や6590円に抵抗線が形成されたとしても、ここをブレイクアウトできなければ、6560円の抵抗線も、やはり効いていたのではないかと考えられます。
黄色のゾーンで示しているように、ここは何重にも重なった抵抗ゾーンだと考えればイメージしやすいのではないでしょうか?
CQGの抵抗線マクロは、意識すべき抵抗線を自動的に描画してくれますから、線の位置が正しいのかどうかということに対して「集中力が分散されない」というメリットがあります。
下は昨夜のGOOGの3分足チャートです。
409.60あたりでショートだったのですが、黄色いゾーンの高値だけを意識すればあとは太い青い線のFix Week
という30分足の抵抗線を意識しておくだけで、どこでショートをすればいいのかが一目瞭然でわかりますね。
このように3分足のチャートで、30分足の抵抗線の位置を知るという、違うタイムフレームでの抵抗線を見ながらトレードをするというケースでは、このガイドラインのマクロは、強力なツールとなります。
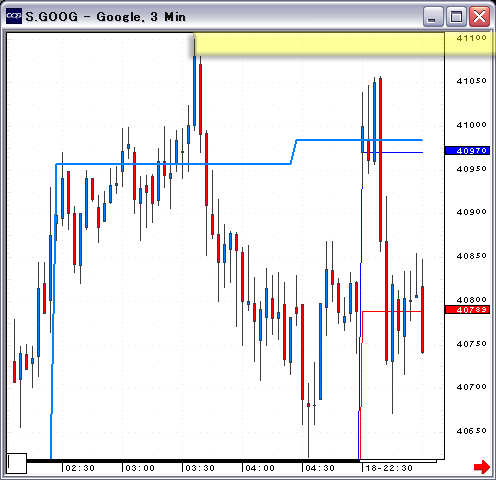
実トレードでは、特にイントラデイのデイトレードの場合、見た瞬間にその抵抗線の位置が瞬時にわかるというのは、大きなアドバンテージとなります。
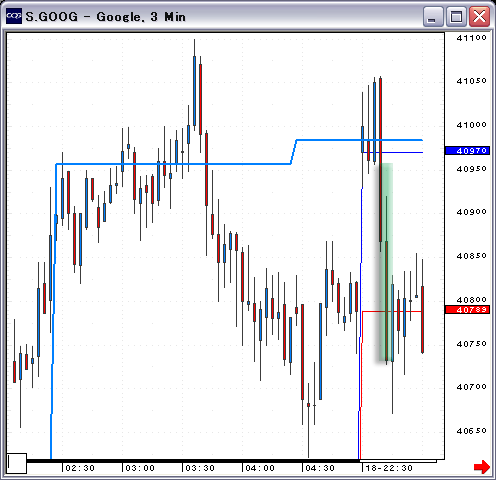
下は1分足チャートです。
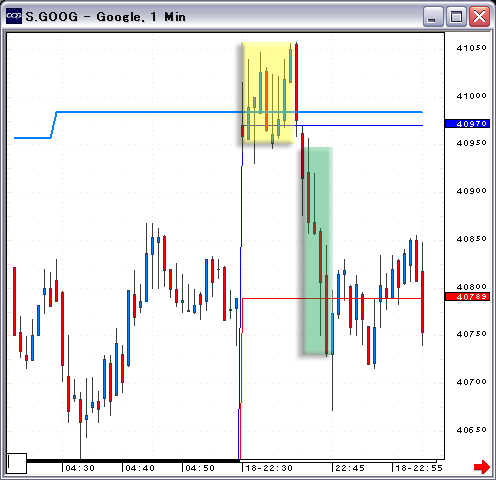
どのタイムフレームへ変えても、30分という大きな流れを掴むためのタイムフレームでの抵抗線を瞬時に自動描画してくれる機能は、実トレードで一度でも使ったことがある人なら、その有難さが良くわかると思います。
複数のチャートを見比べるといういわゆる集中力を分散させる要素がなくなり、チャートに集中できるのですからね。
一度使うとやめられません。(笑)
Live Aid index へ戻る