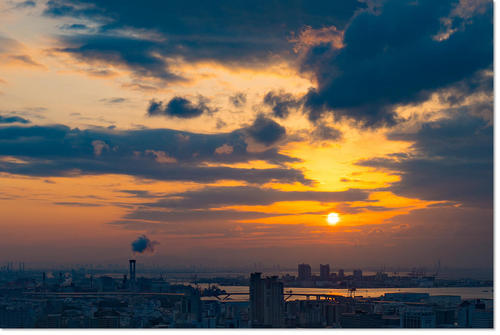たまたま録画されていた日本映画。
日本映画には散々懲りていたはずが・・
日本アカデミー賞10冠・衝撃の感動作というサブタイトルに釣られてしまった。
映画 『八日目の蝉』 予告編
タイトルは「七日目で死ぬはずの蝉が、八日目まで生き長らえたとしたら幸せなのか?」という問いかけから来ているのだという。
なお、読んでゆくと筋などがネタバレするので、ご承知あれ。

左が誘拐されて大きくなった子供役。
右は誘拐犯である育ての親役。(見たたことのある顔)
映画が始まると、生みの母親が真正面からのドアップで、延々と心情を説明し始める。
ここで即こりゃあ、ダメだと思ったのだが、まだ始まってたった5分ほど。
気を取り直して観ていると、今度は誘拐して4歳まで育てた母親役が登場。
ここでも、同じように真正面からのアップで延々と説明を始めるのだった。
いきなりのダブルパンチ。
何故冒頭で説明しまくるのだろう?
このシーンで説明する内容は、その立場なら誰でもそう思うだろうなという心情が吐露されている。
わざわざ説明する必要は全くないと思う。
冒頭で説明する内容というのは本来、役者が演じることで、観ている側に伝えるのが役者であり、また監督の力量なのではないだろうか。
つまり、この冒頭シーンがあることで、謎解きの楽しみは全くなくなってしまっている。
さて、この生みの母親役がいろんな意味で、クセモノだった。
4年ぶりに戻ってきた子供を寝かしつけるシーンが出てくる。
ここで、子供は、何チャラの歌を歌って欲しいとせがむのだ。
だがあいにく、生みの母は子供が歌ってほしい曲ではない曲を歌ってしまう。
で、子供が違うと言うと、別の曲を歌うのだが、それも違っていたのだった・・
そこでいきなり生みの母は、半狂乱になり、夫に羽交い締めにされ、なだめられることになる。
何かに憑依されたように、いきなりまるで別人になてしまうのだ。
そりゃあ誰だってビックリするわけで、これじゃあまるで、ホラー映画ではないか。
あんなに暴れなくても、目で演技できるはず。
その方が真実味があろうというもの。
あれじゃあ、生みの母ではなく、まるで小学生じゃないか。(笑)
そのあとこの生みの母が登場するのは、娘から子供を産むので金を貸せとせびられる場面だ。
そこで、生みの母は感情的になって今度は包丁を掴むのだ。
ありゃあ、またか。
一体どうしたというのか?
娘がアンタを襲うなんていう気配は、微塵もないのにだ。
別に包丁をハラの前で握り締めなくてもいいだろう。
精神的にちょっとおかしくなっている、ということを言いたいのだろうか?
その前のシーンでも、この生みの母は、娘に向かって、彼と別れたのなら、子供は生まずに堕ろせという。
何たることをサンタルチア。(笑)
というわけで?この映画では、このあと生みの母は全く蚊帳の外となるわけで、これじゃあねえ。
なわけで、大きくなった子供には疎まれてゆくという設定になっている。
この時点で、エンディングが娘が生みの母との心温まるシーンで終わる、という可能性はゼロになってしまっている。
ある意味で、能書き通りの「衝撃の感動作」ではあるわけだが、本来そういう意味ではないはず。
感動したい気持ちを逆なでするかのようなシーンが邪魔をする仕掛けになっている。
音楽がまた良くない。
日本人男性による英語の巻き舌歌詞による曲が登場するが、この曲が流れると、映画全体の印象がチャラくなってしまう。
何だかなあ・・

右側が記者役
冒頭のシーンが終わると、すぐに記者が登場する。
彼女は誘拐された子供がしばらく住んでいた、ワケありの女ばかりで自給自足の共同生活集団「エンゼルホーム」天使の家?という怪しげな宗教団体のようなところで、一緒に遊んでいた友達という設定だ。
この記者役の小池何チャラという御仁は、雑誌のプロの記者という設定になっている。
誘拐された子供との天使の家での「幼なじみ」という点しか説明されていないため、まるで好奇心一杯のシロウトによるヘンタイ趣味のストーカーのような振る舞いに見えてしまう。
記者の所属する組織や、彼女の背景に関する描写は一切なし。
しかしこの女優は、典型的な大根役者だよなあ・・
しかも、「天使の家」の教祖役というのが、わざとらしい「いで立ちと演技」で追い打ちを掛けるわけだ。

右が教祖
そのため、すっかり嘘臭くなってしまっている。
次に誘拐した母親役について。
赤ちゃんに授乳するシーンがあるのだが、乳房が見えると困るのだろうか、ブラジャーの下から赤ん坊の頭を突っ込もうとするのだ。
それじゃ赤ちゃんは苦しいだろうが・・
子供を育てた母親なら、このシーンがいかに不自然に映るのかは言わずもがな。
そんなに見せたくないのなら、見えない角度からの授乳するショットにすればいいだけのハナシだ。
感情移入したくなるたびに、こうした些細ではあるが確実に気になる点が出現する映画だ。
この映画も何チャラ制作委員会というのが冒頭にクレジットされている。
この方式はスポンサー数が増えることによって、作品のクオリティや責任までもが分散されるという弊害があり、妙なシーンがあっても誰も軌道修正をしようとはしなくなるわけだ。
オレ的に言えば「映画の題名・制作委員会」というのが出てくる映画はまずダメ。
この映画も、定説の範疇を超えるモノではない仕上がりとなっている。
だが、ストーリーの元になる設定自体は決して悪くない筋書きだ。
問題はエンディングではないだろうか。
希有な体験をして成長した娘は、最後に子供を産むと言う点に希望を見いだすのだが・・
それじゃあ、ちょっと「ありきたり」過ぎるのではないだろうか。
誘拐という悪事を働いたものの、それでも愛を注ぎ4年間育ててくれた育ての母。
その親の愛情に対して、育てられた娘との何らかの心が通じあうシーンがあれば、観客の気分はずいぶん違ってくるはず。
別に生みの母でもいいわけだが、冒頭シーンでの振る舞いがあるからねえ。(笑)
そのため、そのエンディングは無理筋となってしまっている。
残る選択肢は、やはり「育ての親の愛情」という選択肢にならざるを得ないわけだ。
生みの母と、犯罪ではあるが愛情をかけて育ててくれた母。
その狭間で苦しんだ娘に、救いの色がないというのでは、ちょっと切ない気がする。
映画館を出るとき、作品を観た者が自然に「心温まる」心持ちになってしまう作品。
そうした映画であったなら、日本アカデミー賞を10冠も、与える必要はなかったのではないだろうか。
関連記事
日本映画は何故面白くないのか?
亡国の日本映画
日本映画
武士の一分
東京家族
ぽっぽや
映画は脚本だよね
映画評論の書き方
動画撮影の壁とは?
三脚穴付スマートフォンホルダー