3月14日号のニューズウィーク誌で「住めば住むほど得する理想の住宅」という特集が組まれていました。
「30年後も快適に暮らせて資産価値も保てる住宅作りの条件を世界に学ぶ」というタイトルの興味深い記事でした。
そこで今日は、この記事からざっと要点をまとめ、昨日の日記の関連した部分について言及しておきたいと思います。
ニューズウィークではまず冒頭で、「買うなら中古住宅というのが世界の常識だ」と断言してます。
日本の住宅は寿命が短く、マンションや戸建てをあわせた全住宅の平均寿命は45年。
一方諸外国ではアメリカは71年、ドイツは141年、イギリスは143年もの長寿命なのです。
日本の木造住宅は、税法上では20年から22年、鉄筋コンクリートでは47年が経過すると、法定耐用年数になるため、市場では賞味期限切れとなります。
欧米では中古住宅市場が確立されているため、売買される住宅における中古の割合は、アメリカで77%、イギリスで86%、フランスでは71%と高いのですが、日本ではこうした寿命の短さの影響でしょうか、たったの13%でしかないのです。
日本以外の国では家の寿命が長く、住宅が資産になるのはなぜなのでしょうか。
たとえばイギリスには、地域全体の徹底管理で一等地に成長した住宅街があります。
ドイツでは、劣エネ認証の取得が住宅の価値を決める条件となり、消耗する設備の交換を念頭に置いた住宅「スケルトン・インフィル(SI)」や、エネルギー効率を高める「高断熱住宅」など、住宅の質を劣化させない仕組みがあります。
アメリカでは欠陥や偽装工事を防ぎ、建物の品質を確保する「コンストラクション・マネジメント」や、民間と政府による徹底検査などの管理体制が確立しています。
ですが日本の古いマンションでは、水回りの故障が深刻で、多くのケースでは配管の詳しい設計書は残っていないことが多いのです。
一般に住宅が20年から30年が経過すると、まず問題になるのは配管のサビです。
水が赤褐色に濁り、次に継ぎ目からの漏水が始まるのですが、耐久性の高い材質の配管でも、寿命は30年から40年ほど。
さらに、日本の古い住宅では配管の交換が、むずかしいケースが多いのです。
とくに主給排水管は、建物内の各住戸の壁の中の専有部分にあり、配管の設置が複雑で改修費用もかさむため、住民の同意を得るのがむずかしいのです。
一方、欧米の共同住宅では、配管などの交換については、はるかに容易に設計されています。
共用の縦配管は各戸の専有部分ではなく、住戸の外側の共有スペースへまとめ、各戸に延びる横の配管も床下や天井裏の空間に収めるのが一般的です。
私がアメリカで学んだことの一つは、購入予定の投資物件を見る際には、必ずこうした配管部分をチェックするという点でした。
かなり古い物件でも、アメリカではガスと上下水道の配管は通常床下にあり、床を上げれば比較的簡単に交換できるようになっています。
こうした発想の延長線上にあるのが、機能性を追求した「スケルトン・インフィル」で、集合住宅を耐用期間が100年ほどの構造体と、30年ほどの内装・設備に分けて考え、内装の取り換えを容易にしたシステムで、オランダで40年ほど前に提唱されたものです。
こうした点がすでに取り入れられている多くの一般欧米住宅は、古いにもかかわらず価値は上がるのが普通です。
日本ではデザイナーズ住宅というのは人気があるのですが、欧米では資産にならないケースが多いのもまた、日本と欧米との大きな違いです。
資産としてはデザインより立地や歴史的価値が評価されることが多く、有名建築家が手がけた住宅も、大半は無名の建築家の建物と大差ない価格で流通しています。
有名建築家の奇抜な住宅は歴史の検証を受けていないため、アメリカの金融機関ではリスクと考えられ、融資の評価は低くなることの方が多いのです。
またデザイナーズ住宅では耐震面のリスクが多いのも問題となっています。
建物は上から見た重心と耐力壁のつり合いで見た剛心が近いほどバランスがよいのですが、ザイン性を追求するほど、二つの中心の差は大きくなるのです。
耐震基準をクリアしても、安全性で差が出る場合があり、耐震性では建物は直方体が理想なのです。
日本は戦後、住宅不足を解消するため、一貫して量の拡大をめざしてきました。
ですが今後訪れる人口減少と高齢社会では、住宅が余る一方です。
国も今後、中古住宅を重視すると宣言しはじめていますが、そうしたまさに転換期を象徴するような出来事が2005年の耐震偽装事件でした。
住宅の質に対する信用を確保できなければ、中古住宅の取引の基盤は根底から崩れます。
どうすれば流通する住宅の欠陥や手抜き工事を見抜けるのか。
アメリカでは検査確認体制は厳重で、地方自治体の建築検査員が基礎、配管など工事の各段階で検査に入るうえ、施工者や建築主とは無関係の民間検査業者(ホームインスペクター)による検査の2本立てになっています。
新築住宅の50~75%はホームインスペクターの検査を受けるのです。
なぜなら検査を受けていないと、高い値段では売れないからです。
さらに集合住宅の場合、「コンストラクション・マネジメント」という効率的かつ経済的に建設を行うための考え方が業界に浸透しています。
これは、建材や人件費の予算の細目から工期にいたるまで徹底的に管理することで、建設過程の透明度を高めるものなのです。
施主側に立って施工業者を監督し、予算に見合う品質かどうか確かめるのがコンストラクション・マネジャーの仕事で、全米で約43万人がこの仕事に就いています。
ですが、日本の住宅事情が戦後一貫して悪いままだったわけではなく、日本の住宅1戸当たりの延べ面積は78年の約75平方メートルから、98年には約90平方メートルと、イギリスと同程度に増加しています。
住宅の寿命も今後は、延びる傾向にあります。
これまで短期で壊された建物の多くは、高度成長期までに建てられた低水準のもので、60%を占める80年以降の住宅は、高齢化で、建て替える経済力もなくなるため、壊される可能性は低くなるはずです。
木造家屋が密集していた江戸では、大火事が頻繁に起き、明暦の大火(1657年)では江戸の半分が焼け、10万人の死者が出ました。
150年ほどの間に、記録に残る大火が10回もあったのですが、地震や火災など頻繁に起こる天災への無力感が、日本人の刹那的な住宅観を生み出したともいえるのかもしれません。
農家の家などのしっかりした家は伝統的に長もちをするのですが、こうした背景のため、日本では庶民の家はほとんど残らないのです。
さらに日本では地震が多いという特殊な事情が存在しています。
2006年の12月末に、耐震強度偽装事件の「実行犯」姉歯秀次元一級建築士に罰金180万円、懲役5年の地裁判決が下されました。
ですが、その後も住宅の欠陥や偽装を防ぐ法整備はいっこうに進んでいないのが現実です。
新しい耐震基準を満たさない中古物件も、全国に数えきれないほど残っています。
たとえ政府の規定をクリアしても、絶対安全とはかぎらないのです。
現在、新築の建物は81年6月に改正された建築基準法の新耐震基準を満たすことが義務づけられています。
ですが改正前に建てられた中古マンション・住宅は、改修しなくても法には触れないのです。
こうした「既存不適格」の建築物の危うさは、95年の阪神淡路大震災が証明しています。
当時の犠牲者6400人以上のうち、8~9割が建物の倒壊による窒息死、圧死で、その大半が81年以前の建物で亡くなっているのです。
2006年1月、政府は建築物の耐震改修促進法を改正し、15年までに81年の基準を満たす建物の割合を90%に高めるため、地方自治体に改修促進計画の策定と補助制度の整備を求めています。
ですが実際は、所有者は資金の問題で、なかなか建て替えに踏み切れないのです。
法律で定めているのはあくまで最低ラインで「住人が死なないように」という基準です。
これは大地震のたびに改定されてきました。
78年の宮城沖地震の後に81年の新耐震基準、95年の阪神淡路大震災の後に2000年の新新耐震基準が定められました。
予想される東海大地震や首都直下地震では、揺れの激しい地域は震度7が想定されています。
ですが81年の基準は、震度6強以上では「倒壊を免れること」を目標にしたもので、実際に大地震が起これば、「倒壊しなくても多くの建物が居住不能となり、住民の多くが二重ローンをかかえて苦しむことになるのです。
そのため専門家は、強い地盤と弱い地盤で基準を変えるべきだと主張しています。
いくら建物の構造や基礎を強固につくっても、地盤が悪ければ建物自体が沈下してしまうからです。
今の法整備では、手抜き工事や偽装がひそかに行われても見抜く手だてはありません。
昨年、建築基準法と建築士法が改正され、建築士などの違反行為への罰則強化や構造専門家による適合性判定や、一定の建築士に講習を義務づけるなどの変更が行われました。
ですがその実効性には疑問が残るのです。
今国会では、欠陥住宅による被害を補償する制度の法案提出が見込まれています。
成立すれば、欠陥住宅の売り主が倒産しても被害者側が二重ローンで苦しまないように、保険と供託金で建て替えを行えるようになります。
現時点では、保険に加入しているマンション販売業者は全体の12~13%程度なのです。
ですから、どの業者を信頼すればいいのかという点については、消費者が見極めなければならないのです。
国土交通省の関係者は消費者が厳しく売り主を選別するしかないと自己責任を強調するだけなのです。
私は渡米時に、コンサルティング会社やアメリカの不動産のプロから多くを学び、その結果として、日本のマーケットの不動産ではなく、アメリカの不動産を選択しました。
10年前に米国で当時購入した不動産と、現在の日本の不動産の価値を比べると、どちらの物件がよい買い物だったのかは一目瞭然です。
幸いにも仕事としてだけではなく、アメリカで自宅としての中古の住宅を2度も売買した経験は、こうした点を考えるときに、とても役立っています。
ですからこうした不動産については、私自身が身をもって体験したことも加味しながら書いているのですが、この点こそが机上で議論を重ねるだけの、売り手サイドのバイアスの掛かった人たちとの大きな違いだと自負する次第です。
出典
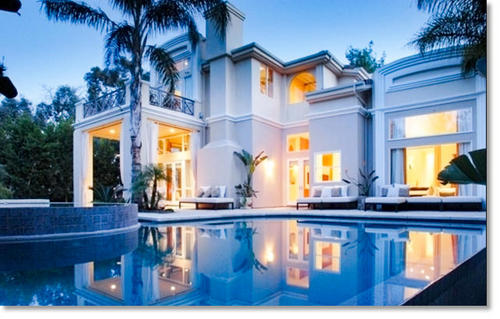
コメントする