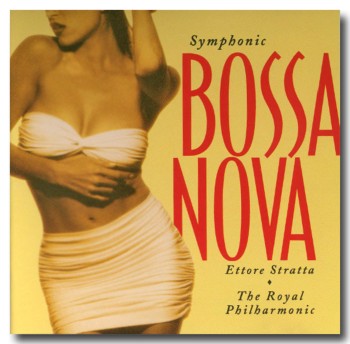The Royal Philharmonic Orchestra conducted by Ettore Stratta
エットーレ・ストラッタ指揮ザ・ローヤル・フィルハーモニックスオーケストラ
このアルバムは洗練されたアレンジによるボサノバの名曲を素材にして、トップクラスのジャズプレーヤー達による気迫溢れるプレイが収録されている。
ストリングスを中心としたバッキングは、あのローヤル・フィルハーモニックスオーケストラ。
リズム・メロディー・ハーモニーを高いレベルで融合させた、これぞまさしく究極のフュージョンと呼びたい、20年近く聴き続けてきたアルバムをご紹介。
一曲目は One Note Samba / the Girl from Ipanema。
それぞれの曲でアドリブパートが用意され「タラタラ流れるお茶の水」で終始することなく「聴かせよう」とする明確な意図によってアレンジされている。
素晴らしい音色のソプラノサックスの、あまりのシンコペーションの食い付きのよさに、只者ではないなとクレジットを見ると、何と Tom Scott。
the Girl from Ipanema では、トム・スコットによるテナーのアドリブソロを存分に堪能することができる。
Ettore Stratta - "Atras da Porta"
二曲目Atras da Porta のイントロでは、このアルバムの根底に流れているエモーションを感じる素晴らしいオーケストレーションを味わうことができる。
そしてトロンボーンのテーマに典型的なエレピのサウンドが絡み、そのあとには甘美な弦が美しいメロディーが展開されるという寸法だ。
途中からアップテンポに変わり、そこではフリューゲルホーンがアドリブを取るが、バッキングのオーケストレーションの厚さに加え、フルートが加わるリフを聴くと、アレンジのグレードが只者ではないレベルで施されていることがわかる。
しかし二曲目でこれだけの演奏が楽しめるとは・・
三曲目のBerimbau は ヴァイブがメインとなるミディアムアップテンポのナンバー。
コードチェンジの妙に加え、Gary Burton のヴァイブによるアドリブソロが、ゴキゲンなボサのリズムに乗って展開される。
バッキングでは16分のシンコぺーションがリズムにキレを加え、ビビッドな味わいの演奏となっている。
しかし、後半の弦のテーマとのスリリングなコードアレンジは鳥肌もの。
しかもエンディングはゲイリー・バートンのアドリブでもってフェードアウト。
Like a Lover はあのアル・ジャロウの歌が堪能できるナンバーだ。
アルジャロウはクセがあるだけに、彼のアルバムだとどうしても少し「くどくなりがち」なのは、歌のテクがうま過ぎるための副作用なのかもしれない。
だがこのトラックでは彼のボーカルの持ち味が、オーケストラとほどよくブレンドし、前後のトラックとの配置もよいこともあいまって、アルの「おいしさ」をしっかりと味わうことができる。
歌の後で繰り広げられるピアノによるアドリブソロが、リリカルで美しい。
五曲目のCurumin はまさにリズムの競演。
絢爛豪華という表現にぴったりのリズムだ。
オーケストラ、ゲイリー・バートンのヴァイブ、ベースなどが入れ替わり立ち替わり、緻密なスコアリングで構成された音楽を織りなす様はまさに圧巻。
Gary Burton のヴァイブと Jorge Calandelli のピアノソロによる疾走感溢れる展開に加え、しっかりとアレンジされたスコアによるメロディーラインが交差しながら、めまぐるしく変化するリズムの色合いと共に、ゾクゾクするようなスピード感を十二分に味わうことができる。
六曲目の If you went away あたりになると、ムーディーブルースのあの名アルバムを彷彿させる「テイスト」を持ち合わせていることに気づくかも知れない。
やがてスローな4ビートに乗ったサックスのテーマが展開され、やがてトム・スコットのテナーによるアドリブへとなだれ込む。
緩急自在な間の取り方と、バッキングのオーケストラの音の厚さのコンビネーションに加え、エンディングのオーボエのあたりのコードチェンジは、聴くものを幻惑させるかのような効果を生み出している。
ファンタスティック!
Wave のイントロのアイデアの何と美しいことか。
そして例のメロディーをピアノが丁寧に「しっとり」と紡ぎあげてゆく。
サビまわりを繋ぐブリッジになっているフレーズが、とてもお洒落。
夏の強い日差しを受けて揺れる木漏れ日のように、調和と不安のはざまを揺れ動くコードとメロディーが織りなすコンビネーションは、5分20秒という長さを全く感じさせることなく、聴くものを翻弄し続けてくれる。
八曲目のMagic Moment は、まさにタイトルどおりのイメージの曲だ。
ゆったりとした、うねるような抑揚の中で、美しいオーケストラのアレンジとDori Caymmiのカラダの芯を蕩けさせてくれるかのようなスキャットに身をゆだねていると、日ごろの様々なことが記憶から遠のいてゆくかのようだ。
このマジックは音楽だけが持つ魔法のチカラなのだということを、感じさせてくれる。
だがそれだけでは終わらない。
途中からいきなりアップテンポに変わり、声と弦とのユニゾンに、切れのいいドラムのリズムがアクセントを加え、5分48秒という時間を全く感じさせないナンバーに仕上がっている。
Ettore Stratta & The Royal Philharmonic The Island
九曲目は、The Island / Daquilo que eu sei のメドレー。
イントロはフルートによるテーマから始まるが、エッジの効いたアルトフルートの音色は、一流のプレーヤーだけが出せるサウンドだ。
それもそのはず、クレジットを見るとあの名手 Hubert Laws によるもので、6分54秒という長さは、嬉しいことに後半の目くるめくような、ヒューバート・ロウズのスピード感溢れるアドリブソロが含まれているためだ。
鳥肌モノのアドリブソロがフェードアウトする頃には、この曲が7分近くあったことなど、きっと忘れているはず。
Brazil / Bahia では、冒頭から素晴らしいオーストレーションが終始堪能できるアレンジが施されている。
タブラの低音を効果的に生かした、ミステリアスな響きのサウンドは、これから始まる出来事を予感させるかのようで、ゾクゾクするほどスリリング。
リズムを変幻自在に操り、低音域と高音域の楽器のコンビネーネーションの妙までも取り込んだアレンジは、まるで時の流れが止まったかのような世界に、聴くものを誘ってくれるはず。
中程からは地を這うような低音のリズムと共に、エキゾチックなエモーションを存分に感じることができるだろう。
how insensitive - Ettore Stratta
11曲目のHow Insenstive はリズムセクション抜きのイントロ。
原曲の美しさを生かす、淡々としたオーケストレーションのアレンジとあいまって、オーボエによるテーマとのブレンドが心地よい。
リズムセクションが加わると、シンプルで「間」を十分に生かした生ピアノの演奏が始まるが、Mike Renzi によるプレイはリリカルな輝きを放っている。
よいオーディオをお持ちなら、高音のピアノの弦とハンマーがヒットする情景までも、目に浮かぶはず。
manha de carnaval - ettore stratta-the royal philarrmonic
ラストはあの名曲 Manha de Carnival (黒いオルフェ)。
この曲にふさわしい、もの悲しい響きのオーボエの音色が際立つアレンジが秀逸。
そして分厚い弦がメロディーを引き継ぐが、このあたりの音の密度の緩急の具合は、深いダイナミックレンジを感じさせてくれる。
リズムセクションは全く入らないが、最後を飾るにふさわしい「ゆったりと流れる大河」のようなダイナミズムに身を任せ、至福の一時を味わえるナンバーだ。
ほんの二曲ほどのナンバーを紹介するため、聴きながら書き始めたのだが、気がつけば最後の曲が終わってしまったとは・・・嗚呼!